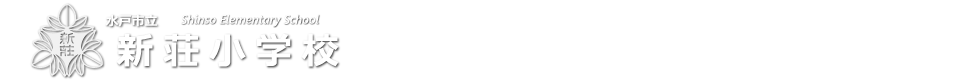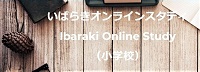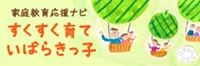校内案内
由緒ある本校学区
かつて,本校付近は「新屋敷」とよばれ,梅・松・楓・柳・花・桜・桃・常磐・柏・桐と名付けられた10の小路がありました。天保年間第9代藩主徳川斉昭(烈公)がこの地を開墾し,江戸小石川邸の勤番諸士を水戸に帰し,この地を与えたのが名称の起こりで,校名・新荘も新屋敷に由来します。現在でも,大工町など当時をしのばせる地名が残り,名所旧跡が多くあります。
我が国三名園の一つでもある偕楽園をはじめ,好文亭,常磐神社,八幡宮などの重要文化財が点在し,歴史的環境に恵まれています。
児童を見守るムクロジ
新荘小学校のシンボルです。
毎日,元気に生活している子どもたちを見守っていてくれているようです。ムクロジの熟した果実は,果皮がつやのある黄褐色の半透明になり,中に一個の黒い種子を含んでいます。種子はとても堅く,よく弾むので羽子板の羽のおもりとして利用されたり,また,煎って食べることもできるそうです。実のまわりの皮の部分を水で濡らしてこすると石けんになるとか…ぜひ,試してみたいと思います。
伝統を誇る管楽合奏部
茨城県吹奏楽コンクール24回連続金賞をはじめ,東関東吹奏楽コンクール金賞,こども音楽コンクール最優秀賞,水戸市褒状受賞など,各種の名誉ある賞を受賞しており,カップや盾,トロフィーを陳列する棚には,数え切れないほどの数が並んでいます。
本校管楽合奏部員は3~6年生で構成され,高学年の児童が下級生へ細やかな配慮でさまざまなことを教えています。活動は,地域の人たちの協力を得ながら,ていねいで効率的に行われています。
5年総合「一粒の種からプロジェクト」
5年生のまごころの学習として「一粒の種からプロジェクト」を行っています。茨城県環境アドバイザーの先生の協力を得ながら数か月かけて育てる、校舎の南面を覆いつくすほどに成長したグリーンカーテンは圧巻です。
植物の栽培だけでなく、地球温暖化への効果や一粒の種がつなぐ命のつながりなど、多くの学びを得ています。
「かえでの子活動」
1~6年生を7の縦割り班に分け、1年間を通して活動しています。日常の縦割り遊びだけでなく、歴史館への遠足や運動会でのかえでの子種目、縦割り班のグループで行う1~3年生の遠足、4・5年生の宿泊学習など行事の中でも縦割り班での活動を取り入れています。6年生はリーダーとしての自覚をもち,下学年の児童は上級生の姿から学びます。学年が変われば、立場や役割が変わり、この活動を継続することで、6年間かけて豊かな心の涵養を図っています。