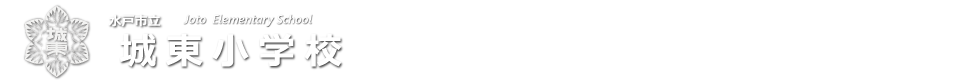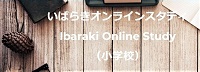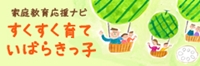ブログ
ありがとうございました
夏休みに入り、気温が高い日が続いています。
学校の放課後学級に通ってきている子どもたちは、規則正しい生活を送っており、学習したり仲間と楽しい時間を過ごしたりしています。その様子から、ご家庭で過ごしている子どもたちも、元気に過ごしていることが予想されます。夏休みに入り、最初の一週間が過ぎようとしていますが、おかげさまで子どもたちの事故等の報告もなく、一安心しています。新聞やテレビのニュースでは、水の事故や交通事故の報道が多くあり、本校の子どもたちの生活も心配になることがありますが、今後も引き続き、子どもたちの安全な生活が続きますよう、保護者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
今週は、二者面談週間でした。お忙しい中また、暑い中、面談にご協力いただきましてありがとうございました。今回の面談を2学期からの生活に生かしていきたいと考えております。
お世話になり、ありがとうございました。
小さな芽


(ちょっと焦点が合っていませんが…)
職員玄関に続く階段を上がろうとしたら『小さな芽』を発見しました。本当に小さくて、だれも気が付かないかもしれないくらいの小さな芽でした。
草かな?花かな?他には見当たりません。これひとつだけひょっこりと顔を出していました。
『小さな芽』に気が付いたら、さて、これをどうしようか?
夏休みになり、子どもたちがいなくなった校舎を歩くと、普段見られなかった景色が見えてきます。
ご家庭では、普段学校に行っていた子どもが家にいる光景から普段見えなかった景色が見えたりしていませんか。
さて、見えてきた景色に気が付いたら、次は何をしますか?
『す』ぜひ、ステキな思い出作ってくださいね。
夏の花壇
頭の体操!
先日、おもしろ算数の授業をしてくださった川又先生が、こんなものをプレゼントしてくださいました。

たねあかしは、『ヒミツ』だそうです。
さあ、みなさん、仕掛けはわかりますか?
ヒントは↓



長い夏休みに、チャレンジしてみましょうね。
職員研修
1学期終業式
7月19日、第1学期終業式が行われました。
湿度が高く、蒸し暑い体育館でしたが、子どもたちは真剣に臨むことができました。

校長からは、夏休みの合言葉『あ・い・す』の話がありました。
『あ』は、『安全な生活をしましょう。』命の大切さを伝え、命をなくすような危険な行為は絶対にしないことを話しました。
『い』は、『一生懸命勉強やお手伝いをしましょう。』めあてを決めて、やるべきことは一生懸命取り組むことを話しました。
『す』は、『すてきな思い出を作りましょう。』遠くに出かけたことだけでなく、地域の人にあいさつしたりゴミ拾いをしたりしたことも、すてきな思い出になるので、2学期に校長先生にお手紙で知らせてほしいことを話しました。
さらに、校庭のポプラの木が切られること、なかよし学級の担任の先生がおやめになることを話しました。
終業式が終わり、教室に戻ると、『あゆみ』が担任から一人一人に手渡されました。



3年生の教室には、茨城新聞社の取材が入りました。(7月20日の新聞に掲載されました。)
一斉下校で集まった際に、代表委員会の児童の進行で、『ポプラの木とのお別れ会』が開かれました。
代表の児童がポプラの木に感謝の言葉を贈ると、みんなで『ありがとうございました。さようなら。』と、大きな声でポプラの木に向かっておわかれをしました。



ふれあいサロンでの交流
毎月第3木曜日に、校舎1階で城東地区ふれあいサロンが開催されています。
今日は、6年生とふれあいサロンの皆さんとの交流会でした。
6年生は、城東地区の歴史について調べ学習をしているので、地域の方々に自分たちの課題解決のための質問をするために計画しました。


おもしろ算数と工作教室

「3年生のみなさん、こんにちは!私は、かわまたといいます。超能力者です。」と、3年生の子どもたちに自己紹介し、棒についた4つのクリップのうちの一つを揺らすパフォーマンスの披露から、授業が始まりました。
子どもたちは、「えー。どうして?すごい?すごい?どうなっているの?」と、歓喜の声をあげました。
川又先生は、市内の中学校の元校長先生です。数学がご専門。今日の『おもしろ算数』も、数の不思議をテーマにして、子どもたちに考えさせていました。45分の授業はあっという間に終わってしまい。子どもたちからは、またやりたいとの声が聴かれました。授業後の振り返りカードには、「マジックみたいな算数が楽しかった。」「いろいろな形の見方があることがわかって楽しかった。」「またきて、いっしょに算数をやりたいな。」などが書かれていました。


昼休みには、2年生の教室で工作教室を開いてくださいました。やじろべえを作りました。鳥の形に切り抜いたものに、色を塗ったり、シールを張ったりして、思い思いのものを仕上げていました。指先に乗せて、バランスを保ちながらゆらゆらさせることができると、あちらこちらから「見て、見て!できたよ!」と、大喜びした2年生でした。






これで 終わりかな?
まごころ学級の子どもたちが、今日の休み時間も職員室にやってきました。

「きたきた!」と、職員室の先生方は、笑顔で迎えてくれました。
「今日は、冷凍の梅です。一袋200円です。」



次の班がやってきました。
「休み時間にとったばかりのピーマンです。一つ10円です。梅ジュースもあります。」
買ってくれた先生には、「取り立てなので、よく洗ってください。野菜炒めがおいしいですよ。」と、伝えることができていました。
今年は、暑さのせいでしょうか、なかなか野菜が収穫できません。1学期もあと3日となりました。
明日も売りに来てくれるかなと、心待ちにしています。
縦割り班清掃
今日は、縦割り班清掃の日です。班ごとに担当場所をそうじする日です。











どの班も上級生が下級生の面倒を見たり、そうじの仕方を教えたりしながら、日頃なかなかできなかった場所を、丁寧に掃除していました。
情報モラル学習
夏休みを前にした本日、全学年で、情報モラルについての学習が行われました。総研のICT支援員さんをお招きし、SNSの使い方、インターネットについて、身近に起こる事件や被害にあわないためになど、具体的な事例を例に挙げながら指導してくださいました。





期末大掃除期間が始まりました
今日は、期末大掃除期間の初日です。今回の大掃除では、あらかじめ子どもたちが、自分たちの清掃場所をどのように掃除するかを話し合いました。今日は、その計画を実行する日でした。
そうじ場所に行き、担当する児童に「今日は、どのようにそうじするのかな?」と質問してみました。すると、「階段の補強テープの端を切って、隅々まできれいにします」と答え、その通りに清掃していました。廊下そうじの児童は「すべらないように注意して、きれいにします」教室そうじでは、「とにかくきれいにします」と、それぞれの場所ごとにしっかりとめあてを決め、それに合わせ忠実に取り組んでいました。









保幼小連絡協議会
5時間目に保幼小連絡協議会を行いました。
1年生、2年生の授業参観をした後、情報交換をしました。



2年生は、タブレットを操作しているところを参観していただきました。幼稚園の先生方は、成長した子どもたちの様子を見て、笑顔で嬉しそうでした。
野菜ができました
まごころ学級の子どもたちが、野菜の販売に職員室にやってきました。入るときには、自分の学年と名前を言うことになていますが、どことなくぎこちない感じから、子どもたちみんな緊張していることが伝わってきました。
いざ販売を始めようとすると、『一袋にピーマンとなすが2個ずつ入って50円です』の声掛けに、買いたいと申し出る先生が多くいて、結局一つずつ売ることとなりました。
さあ、そこで、『一ついくらで売ったらよいのかな?』という相談が始まりました。担任の先生も助けに入り、どうにか値段を決めることができました。これも勉強ですね。



今回の販売も好評で、次回の予約も受け付けていました。楽しみに待っていますね。
ラジオ体操カード
城東郵便局長さんが、夏休みに使うラジオ体操カードを届けてくださいました。


今年は、ポケモンです。40個の枠があるので、夏休みにぜひチャレンジしてみてください。
『継続は力なり』きっと良いことありますよ。
教育長さんがいらっしゃいました
教育長さんがいらっしゃって、1時間目の授業を参観されました。


教室に入ると、子どもたちの学習の様子を笑顔で参観していました。参観後には、「低学年はとても元気でいいですね。高学年になると落ち着いてしっかりと学習していますね。」と、お褒めのことばをいただきました。
今日は、湿度・気温ともに高く、その中で集中した学習をしていた子どもたちでした。






今日の給食 もうすぐ七夕
今日の献立は、『ごはん牛乳星型メンチカツ切干大根のサラダとうがんの七夕汁』です。



もうすぐ七夕ということで、今日の献立になったようです。とうがんのスープには、『星型のかまぼこ』と『魚めん』が使われていました。
給食の献立には、季節感を表現したりや地域の特産を使ったりしたものも多くあります。
7月2日には『パリ2024オリンピック・パラリンピック応援献立』、5日には、『食物せんいたっぷり献立』など、様々なテーマで提供されています。
お手紙ありがとう
『校長先生あのね』ポストには、毎日いろいろな手紙が子どもたちから届きます。

4年生の女の子からは、本校のマスコットキャラクターのそうりゅうくんとたまちゃんが海水浴をしているイラストが届きました。とても丁寧に、そしてキャラクターそれぞれが笑顔で描いてあるので、見ていてとてもやさしい気持ちになります。

先日、梅ジュースと大葉を販売してくれた子どもからは、「来年も売るので買ってくれるとうれしいです」というお手紙です。『はい。来年も買いますよ』と、予約の返事を書きました。

3年生の女の子からは、応援のメッセージです。『こまったときは、おしえてください。できることはします!』と、本当にうれしいメッセージでした。

5年生の子どもたちからは、「ボールにあなが空いてしまったので、ボールがほしいです!」。もちろんすぐに新しいものをあげてほしいと、5年生の担任の先生にお願いしました。

私の似顔絵なのでしょうか?とても美人で可愛く描いてくれたので、そうだと信じて返事を書きました。私の書いた返事に、また返事をくれました。「よんでこころがあったかかったよ。」の返事に、涙が出そうになりました。返事を書くのが楽しみになりました。また、美人に可愛く描いてくれるかな?

「さんくえーるのはながさきました。」
「?」どんな花かな??すぐに、調べました。『なるほどこんな花。よく見かけるけど、サンクエールというんだ。』ひとつ物知りになりました!

「ぼくは、ふじがらちょうにのっています。7ばんめです」
というお手紙が2年生の男の子から届きました。はて?なんのことだろうと。謎が深まりました。
お手紙をくれた男の子に聞いてみると、吉田神社のお祭りのときに、ふじがらちょうの山車に乗るとのことでした。
お誘いありがとう!

子どもたちは、いろいろな思いや願い、出会ったこと、などを丁寧にお手紙に書いてくれています。
私も一人一人の願いや思い、感じたことなどを考えながら、返事を書いています。
校長室のドアのすりガラスに、子どもの影が映った直後には『ポトン』と手紙が箱に入る音がします。その時、『早く読みたい!』と、私はワクワクします。
NIE実践協力校
本年度から2年間、茨城新聞社より『NIE実践協力校』の指定を受けました。
「何をするのかな?」と、思われる方も多いかと思いますが、子どもたちにとってはあまり身近に感じることがなかった新聞を、学習や生活の中にほんの少し引き込んで(使って)いくことを通して、新聞の良さを知ったり、新聞から得た情報を活用したりしていきます。そして、最終的には、子どもたちに、思考力や判断力、表現力が身に付くことをねらいとし、日々様々な取り組みをしています。
4月23日の茨城新聞にも本校の取組の一部が紹介されましたが、今週月曜日にも、子どもたちの様子が写真で掲載されました。
今後多くのことが掲載される予定です。機会がありましたら是非ご覧ください。
食の指導を行いました。
城東タイム
2時間目が終わると、『城東タイム』という業間休みが始まります。
城東タイムが始まると、真っ先に校庭に飛び出してくるのは4年生です。ボールを抱え、校庭の中央に集まり、ドッジボールを始めます。毎回、男女仲良く、元気に行っています。

同じく、4年生の水かけ当番が校庭に出てきました。「何してるの?」の問いかけに「ゴーヤに水をあげています!」と元気に答えてくれました。


今年は、藤棚を活用して、グリーンカーテンを作ります。ゴーヤができるころには、夏休みに入ってしまうかな?
当番の二人は、ゴーヤの水かけが終わると、私に向かい「先生、こっちの畑にも水をあげていいですか?」と「お願いできるかな。よろしくね。」「はーい」と言うと、すぐまごころ、なかよし学級の野菜たちにたっぷりと水をかけてくれました。ありがとう。


用務員さんたちは、毎日、校庭の除草作業に一生懸命取り組んでいます。刈ったところはきれいになるのですが、翌日には、また伸びはじめあっという間に、クローバーの草原が出現してしまいます。どうにかならないかと、思案していますが、よい方法が見つかりません。
クローバーとのジャンケンにいつも負けている感じです。いつか、勝ちたいな…
大葉ができました
「大葉ができました。一つ10円です。」
元気な声でまごころ学級の子どもたちが職員室にやってきました。


今日は、観察園で育てている大葉をきれいに洗い、丁寧にラッピングしてありました。
「一つ10円です。」という言葉と笑顔で、ついつい先生方は、購入してしまいます。
購入したあとの先生方も、にっこり笑顔になっていました。
『ポプラの木』伐採のお知らせ
本校校庭のシンボルツリーの『ポプラの木』を、伐採することといたしました。
5月末、長野県の公園で高さ10メートルのポプラの木が倒れ、小学生がけがをしたというニュースを受け、本校のポプラの木も水戸市教育委員会を通じて専門業者に点検していただきました。その結果、やはり幹、根、共に空洞化が見られ、危険であるという判定を受けました。その結果を受け、様々な方々と検討をし、この度、子どもたちの安全を優先しようということとなり、伐採することといたしました。卒業生はじめ、地域の方々に、そして本校児童に愛されていたポプラの木だけに、大変残念ですが、倒木の危険を回避するために、このような判断といたしました。卒業生の皆様、地域の皆様、そして保護者の皆様には、どうぞご理解とご協力をよろしくお願いいたします。




作業予定は、現在の所決まっておりませんが、児童の学校生活を考慮し、夏季休業期間中(7月22日~8月26日)のいずれかに行う予定です。
決まり次第、学校ホームページ、保護者メールにてお知らせいたします。
完売御礼

出張から帰ると、職員室の机上に『うめジュース売り切れました』というカードがのっていました。
まだ、購入できていなかった私は、がっかりしましたが、今後、野菜の販売もすることがわかり、次こそはと、楽しみが増えました。
小さな経験の積み重ねが、いずれ大きな自信となることを願って、子どもたちを応援していきます。